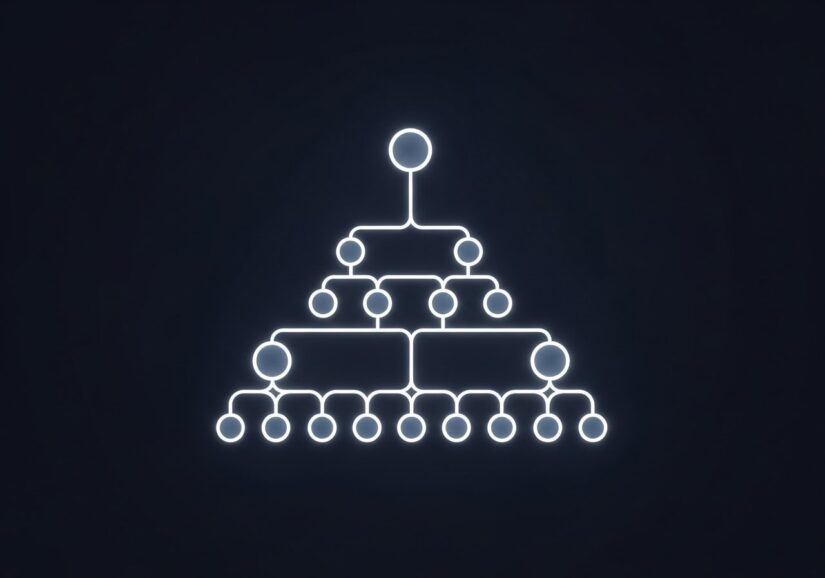前回は、社長の仕事について記事を書かせていただきました。
社長は会社組織におけるトップです。
今回は会社組織とはどうあるべきかについて、私の考えを記載していきたいと思います。
ご存じの方も多いとは思いますが、「識学」という考えをもとにしています。
では、早速行きましょう。
Contents
会社とはピラミッド組織
ほぼ100%の会社はピラミッド構造になっています。
具体的に言うと、社長がいて、役員がいて、部長がいて、課長がいて、一般社員がいるといった感じです。
会社組織に限らず、国会議員でも、学校でも、スポーツチームでも、はたまた家庭でも、基本的にはピラミッド構造になっています。(家庭は違うかな?笑)
役職上位の人が部下を管理・指示する。
部下は上司の指示を実行する。
上司は部下の実行に責任を持つ。
もっと言うと、一般社員は課長の指示、その裏で課長は部長の指示を受けており、部長は役員の指示を、、、というイメージです。
組織を所属している人は、どの立場にいても、ピラミッド構造も意識すべきです。
ピラミッド組織における指示系統
「識学」における一番の基本思想はこのピラミッド構造を崩さないことだと私は理解しています。
つまり、この指示し・指示される関係を崩さない。
さらには役職の飛び越えた指示、コミュニケーションは行わないということです。
ぶっちゃけると社員数の少ない中小企業は、ピラミッド組織という意識は希薄だと思います。
トップは明確ですが、それ以外の社員は実質同率という状況の会社は多いのではないでしょうか。
大企業でも、現場レベルのコミュニケーションは役職を飛び越えることは往々に起こっていることだと思います。
中小企業において、例えば社長から事務の人に直接指示するなんてことは、日常茶飯事で、むしろ組織構造を守っていると仕事が遅くなることは、頻発する事態でしょう。
しかし、社長が見える範囲というのは限られています。
ほどほどの人数で会社を回していくなら、今のままでもいいと思います。
現実問題はさておき、会社をスケールしていくためには組織構造を守るというのは、大きな意味があると思います。
社長などの組織上層部目線で書いていますが、役職者でなくとも得られるメリットだと思います。
デメリットから考えると分かりやすいと思います。
社員の目線に立ってみましょう。
直属の上司から仕事の指示があったとします。
上司の指示通り仕事を進めていたところ、社長から「もっとこうして欲しい」と指摘を受けました。
あなたが部下だった場合ならどうしますか?
部下からすれば、社長の指示を優先するのではないでしょうか。
つまり、直属の上司の「上司としての機能」が低下します。
そして、最終的には社長の判断を仰ぐ回数が多くなり、社長の本来行うべき仕事に割く時間が少なくなります。
組織のピラミッド構造が崩れることで、社長の時間が奪われます。
そして社長個人として裁ける能力以上に、会社は大きくなれません。
口を出したくなる気持ちは十分わかりますが、役職を飛び越えたマネジメントは行うべきではありません。
コミュニケーションコストが減る
社長は役職を超えたコミュニケーション(特に業務に関しての)は行わないことが肝要です。
社長のマイクロマネジメントには限界があります。
部長に指示し、その者に部長以下の社員をマネジメントさせる。
仕事を任せることで、社長の時間が生まれます。
部下(ここでは一般社員)としても、仕事がやりやすいはずです。
なにか困ったことがあれば、直属の上司に指示を仰げばOKという状況は部下の仕事の効率を上げます。
社長の立場においては、部下に気になる点があれば、直下の管理職を通じて伝えることが大切です。
短期的には直接指示をすることが仕事を回す上で早く回るのは確かにそうかもしれません。
しかし、「長い目で見て、コミュニケーションコストが減る」ことは会社を成長させるうえで間違いなく大切なことだと考えています。
最初はコミュニケーションコストが増えることもあります。
しかし、会社を大きくしたいならその労力は惜しむべきではないと考えます。
急成長している企業では、マネジメントを任せざるをえないという状況の社長もいるでしょう。
社長自らマイクロマネジメントできているのは、ただ会社の規模が小さいからという理由が大半ではないでしょうか。
管理職の能力が上がる
管理職の能力が上がれば、任せられる仕事の範囲が広がります。
管理職社員の仕事は、社長の抽象的な指示を具体的な行動に落とし込み、管理下の社員に行動させることです。
例えば、社長から「クレームがあったから、お客様を大切にしよう」という抽象的な指示が出たとします。
これを業務に落とし込み、具体的な行動指針として部下に伝える、そしてその実行をマネジメントするのが管理職の仕事です。
社長が安心して抽象的な指示を出せる信頼を得ることが管理職の腕の見せ所であり、管理職として仕事ができるということです。
社長の能力には限界があります。
優秀な管理職を育てるというのも社長の重要な仕事です。
下から上のコミュニケーション
下から上のコミュニケーションについてもお伝えします。
役職を飛び越えたコミュニケーションを避けるべきだと何度もお伝えしてきましたが、
「下から上のコミュニケーション」についても言えます。
よくドラマなどで、一般社員や部下からの直談判で社長の考えが変わるといった描写がありますが、
現実問題そのようなことはほとんどありませんし、基本的にあってはなりません。
その理由は2つあります。
社長と一般社員の視点が違うから
ほとんど起こらない理由は、社長と一般社員の視点が違うからです。
社長は会社のトップで意思決定及びその責任を持ち、社員は与えられた仕事をするという役割分担があります。
両者のしなければいけないことが違い、前提知識や経験も異なり、見えている世界や目指しているものも違うわけです。
組織運営が難しくなるから
直談判を禁止すべき理由は、組織構造が崩れてしまうからです。
もし一社員の意見を組み入れ、社長が意見を変えて会社の方針を変更したらどうなるでしょうか。
特定の社員を贔屓するわけにはいかないので、他の社員からの意見も聞かなければなりません。
会社にとって本当に有益な意見なら良いですが、そのような場面は少ないです。
以上のことから、下から上のコミュニケーションにも制限を設ける必要があると考えます。
もちろん例外はありますが、基本的にピラミッド構造に従い、社員の意見は直属の上司に伝え、
社長の直属の管理職から社長に報告するという流れが理想的です。
まとめ
正しいコミュニケーションフローに従うことは、長期的に見て会社の成長を支える大きな要因になります。
マイクロマネジメントをやめ、勇気を持って、ピラミッド構造を守る。
部下に仕事を任せる。
会社をスケールさせていく上では大切な考えだと考えています。
次回は「社長が社員に求めてはいけないこと」について書きます。
おまけ
会社経営に限らず組織や人間関係において、がちがちにルールで縛るのも良くないし、
全くルールがないというのも良いことではありません。
“いい感じ”の縛りが何事も必要だと感じています。
家庭における最大の縛りはおこづかい制だと思います。
私は断固拒否し、平穏な日々を送っています。
最後まで読んで頂きありがとうございました。